
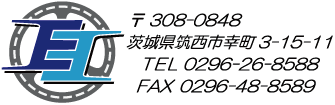

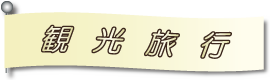
お客様のご利用目的に合わせてお選びください。
茨城観光旅行貸切バス
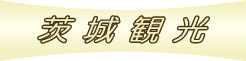
A コース 行先案内
【笠間焼の特徴】
笠間焼の特徴は江戸時代以来の伝統を保持しながらも、それに捕われない自由な作風にあります。また、釉薬流し掛け、重ね描き、青すだれ、あるいは窯変といった釉薬による装飾技法も大きな特徴であり、現在も民窯で行われ、独特のぬくもりのある暮らしの焼き物になっています。
【笠間焼の粘土】
笠間焼きで使用される粘土は、笠間地区より筑波山にかけて産出する花崗岩(御影石)が自然に育まれて風化堆積して生じた粘土です。この粘土は、粘りが強く、整形がしやすいだけでなく、鉄を含むため、焼成後には有色となる特徴があります。この粘土を用いた焼き物は、縄文時代から現在まで受け継がれています。

「笠間市HP」より
≪袋田の滝≫
茨城県久慈郡大子町袋田にあり 日本三名瀑の一つに数えられています。久慈川支流の滝川上流にあたり、高さ120m・幅73mの大きさを誇ります。冬は「氷瀑」と呼ばれる、滝が凍結する現象が発生します。
【四度の滝の由来】
大岸壁を四段に流れることから、別名「四度の滝」とも呼ばれます。滝川が四段に岩肌を落ちることから名づけられたとされる説と、その昔、西行法師が訪れた際に「四季に一度ずつ訪れてみなければ、本当の良さは分からない」と絶賛したことから名付けられたとも言われています。

「大子町HP」より

≪笠間焼≫
笠間焼とは、江戸時代安永年間(1772~1780)に箱田村の久野半右衛門が、信楽の陶工長右衛門の指導をうけたのが始まりと言われています。半右衛門が築いた窯を瀬兵衛が引き継ぎ、長右衛門の弟の吉三郎とともに盛り立て、現在にまで継承される焼き物を確率したと考えられています。